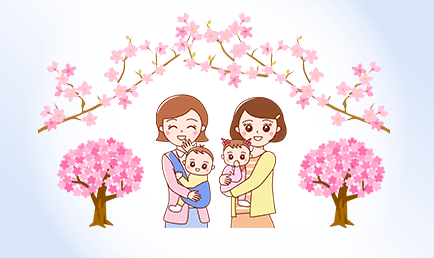2025.03.19
ページ番号:220
配偶者の病気を理由とした離婚はできる?
配偶者が病気になったとき、夫婦関係に様々な困難が生じることがあります。そのため、そのような状況で離婚を考える方も多いと思われます。今回は、配偶者の病気を理由に離婚を考える際の重要なポイントについて詳しく解説します。
1. 病気を理由に離婚を考えてもよいのか?
配偶者が病気になると、その病気の程度にもよりますが、中には日常生活が大きく変わり、介護による負担や経済的負担が増えることがあります。このような状況で、離婚を考えること自体は間違っているわけではありません。夫婦それぞれの人生や価値観を尊重し、個々の幸福を追求するために、離婚が必要と感じることもあると思います。
日本の法律では、離婚は夫婦双方の同意に基づいて行われるのが基本です。しかし、離婚の理由として「病気」が直接的に挙げられることは稀です。法律上、夫婦間には原則として相互扶助義務(民法第752条)があり、配偶者が病気にかかったからといって、すぐに離婚できるわけではありません。裁判で離婚を求める場合だと、法定離婚事由が必要となりますが、その一つとして、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に離婚が認められるとされています(民法第770条1項4号)。
具体的には、統合失調症や認知症など、重度の精神病にかかった場合には、上記事由に該当する可能性があります。ただし、道徳的な観点から、自分自身が病気の配偶者を見捨てるように感じることもあるため、決断は慎重に行う必要があります。
2. 配偶者の病気を理由とした離婚が認められないケースはあるのか?
配偶者の病気を理由に離婚を希望しても、離婚が認められない場合もあります。双方の合意による協議離婚では、離婚理由は問われませんが、裁判で離婚するにあたっては、先ほど述べたとおり、法定離婚事由が必要となります(民法770条1項)。離婚の許否について、裁判所は、精神病の症状や程度、介護の経過や離婚後の見通しなどを考慮して判断します。
例えば、精神病の程度が重大であり、これによって夫婦関係が破綻するほどである場合や、配偶者がこれまで献身的に介護や療養をサポートしてきたといった場合には、離婚が認められる可能性があります。他方、病気の配偶者の今後の療養、生活についてできる限りの具体的な支援措置を講じ、その見込みがつかなければ離婚を認めないとする裁判例も存在します。
もっとも、近年では重度の精神病であっても治療法や治療薬などの発展により、必ずしも「回復の見込みがない」とはいえないケースが増えてきています。
これを踏まえて、令和6年民法改正では、上記の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という法定離婚事由が削除されることが決定しました。そこで、今後は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるか否かが離婚の許否を判断する上で重要な争点となるでしょう。
3. 自責の念に駆られる懸念点は?
配偶者の病気を理由に離婚を考える際、感情的な負担や自責の念が生じることも多く見られます。「病気の配偶者を見捨ててしまう」という罪悪感や、周囲からの非難を恐れる気持ちが、決断を妨げる要因となり得ます。また、長年連れ添った情や責任から、病気の配偶者をサポートし続けることが自身の義務であると感じることもあります。
このような自責の念に駆られている場合には、お一人で悩むのではなく、第三者の助言を受けることが重要です。カウンセラーや弁護士に相談し、自分の気持ちや状況を冷静に整理することで、適切な判断を下す助けとなります。また、家族や友人のサポートを得ることで、罪悪感を減少させ、決断を前向きに考えることができるかもしれません。
行政機関の相談窓口等も利用することで、離婚に関する不安や自責の念を軽減し、適切なサポートを受けることができますので、お悩みの方は、お早めに相談しましょう。
配偶者の病気を理由に離婚を考えることは、法律的にも感情的にも複雑な問題です。離婚を決断する際には、病気の影響や今後の生活を慎重に考慮する必要があります。特に、法的な面だけでなく、感情面でのサポートも重要となります。
離婚が最善の選択肢であると確信できる場合には、適切な手続きを進めるとともに、自責の念に囚われないよう、専門家の助言を得ることが大切です。
この記事を書いた人
弁護士 坂本志乃 弁護士法人Nexill&Partners (旧:弁護士法人菰田総合法律事務所)
福岡県福岡市出身。九州大学法科大学院修了後、2016年弁護士登録。同年に弁護士法人菰田総合法律事務所入所。入所当初から離婚や相続等の家事事件を中心に経験を積み、中小企業支援に業務分野を広げ、現在は企業労務に注力している。